 未分類
未分類 自分のためにお茶と音楽を
親の介護と、自分の問題がかさなって気持ちが沈んでいた時、友人が手伝いに駆けつけてくれました。彼女は片付けしながら、食器棚からカップを選び、きれいに洗ってお茶を入れ、CDをかけて音楽を流しました。生きている間にはさまざまな問題があり悩みは尽き...
 未分類
未分類 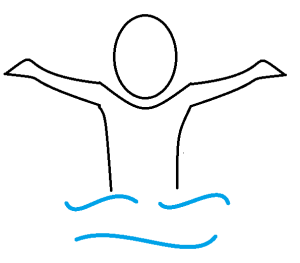 未分類
未分類  雑貨
雑貨  花
花 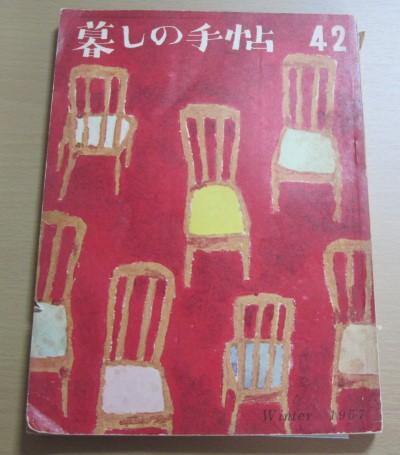 思い出
思い出